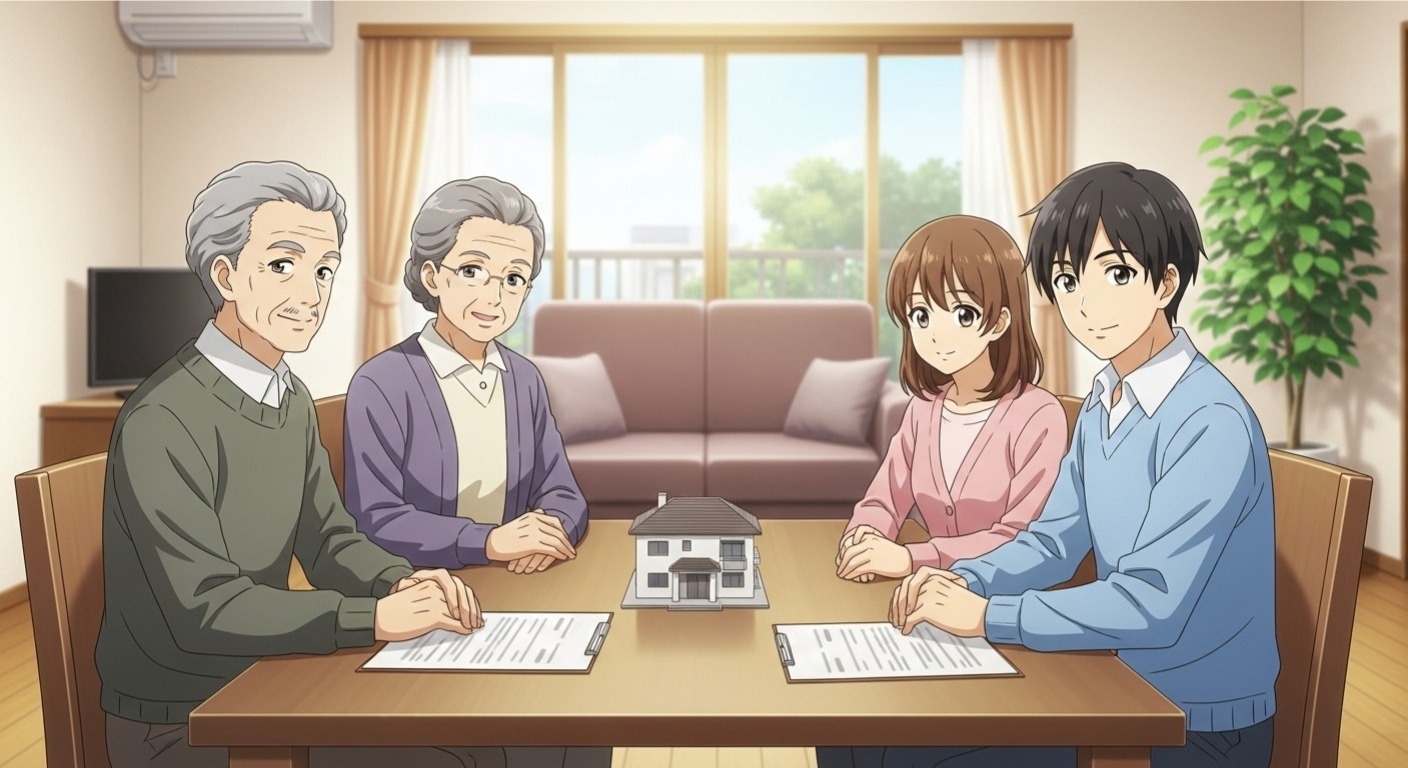
両親が高齢になると、「実家が空き家になったらどうしよう…」と不安になりますよね。実際、2023年時点で国内の空き家は約900万戸に達しており、2018年の空き家率13.6%からさらに増加中です。放置すると倒壊や不衛生化、犯罪リスクが高まるほか、行政から「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍に跳ね上がる場合もあります。
こうした事態を避けるには、早めの家族間の話し合いと対策が不可欠です。本記事では、増え続ける空き家問題の背景を押さえつつ、家族で話し合うべき内容や名義・相続対策、活用方法などを事例・データを交えて詳しく解説します。最後に、便利な不動産プラットフォーム「HomeLinQ」への案内もご紹介します。
空き家問題は「予防が最善の解決策」です。親が元気なうちに対策を始めることで、将来の負担を大幅に軽減できます。
実家が空き家になる典型的なパターンと発生件数の推計
空き家が生まれる主な原因は、家を所有する高齢者が老人ホームなど介護施設に入所することや、子ども宅へ同居することです。また、所有者の死亡による相続も多く、実に空き家取得経緯の55%が「相続」だと報告されています。
📊 空き家発生の原因と将来予測
空き家取得の経緯
- 相続:55%(最多の原因)
- 転勤・転居:約17.1%
- 入院・施設入所:約10.8%
- 贈与:わずか3.3%
深刻な将来予測
- 2013年:約820万戸(全住宅の7戸に1戸)
- 2023年:約900万戸(現在)
- 2033年予測:2,150万戸(全住宅の3戸に1戸)
- 増加要因:少子高齢化と人口流動の変化
🚨 都心部でも無関心は危険
東京都世田谷区の事例
東京都世田谷区だけで5万9000戸超の空き家があるといわれ、都心部でも無関心なままにしておくリスクは高まっています。特に郊外や地方では空き家の急増が懸念されており、こうした統計からも事前の検討・対策の必要性は明らかです。
総務省の住宅・土地統計では、このような増加の裏には、少子高齢化と人口流動の変化があり、特に郊外や地方では空き家の急増が懸念されています。これらの統計は、私たちが「まだ大丈夫」と思っている間にも、確実に進行している現実を示しています。
家族間で話し合うべきポイント(会話例つき)
まずは家族(とくに親)と実家の行く末についてオープンに話し合うことが大切です。早めに話し合うことで、相続トラブルの防止、手続きの円滑化、経済的リスクの軽減に繋がります。
💡 早期話し合いの3つのメリット
- 相続トラブルの防止 - 将来の管理や売却方針を共有せずに放置すると、誰が維持費を負担するかで子ども間の争いになりかねません
- 手続きの円滑化 - 事前に「遺産に家が含まれる」ことや「空き家にするか売却するか」など方針を確認しておけば、いざというときにスムーズです
- 経済的リスク軽減 - 固定資産税や維持費の負担、税制優遇の活用などを事前に計画できます
💬 話し合いを始めるタイミングと切り出し方
話し合いを始めるタイミングとしては、お盆や正月など親戚が集まる機会や、親の健康診断・入院を機に「体調のことを考えると家のことも整理したいね」と自然につなげるのがおすすめです。いきなり「相続はどうする?」と切り出すと驚かれるので、まずは両親の想い出話や健康状況に触れてから本題に入るとよいでしょう。
💬 実際の家族会話例
🌟 自然な切り出し方の例
💡 親の気持ちを引き出すコツ
📝 具体的な確認事項への発展例
💬 会話のポイント
成功する会話の3つの鍵
- 親の思いを尊重 - 一方的に決めるのではなく、親の価値観や希望を第一に考える姿勢を示す
- 協力を求める姿勢 - 「一緒に考えよう」「教えて欲しい」という協力的なトーンで話す
- 具体的な不安解消 - 「負担にならないように」「安心できる方法を」など具体的な安心材料を提示
📋 話し合いで確認しておくべき事項
このように親の思いを尊重しつつ協力を求める姿勢で話すことがポイントです。なお、話し合いの中で確認しておくべき事項は以下の通りです:
📝 重要確認事項チェックリスト
財産・費用関連
- 固定資産税や維持費の負担 - 現在の年間費用と将来の負担予定
- 不動産の名義 - 現在の登記状況と名義人の確認
- 住宅ローンの有無 - 残債や団体信用生命保険の状況
- 建物の状況 - 修繕必要箇所や築年数の確認
将来計画関連
- 家の活用意向 - 住み続ける・売る・貸す・解体など
- 今後の住まい - 介護施設・二世帯住宅・子ども宅同居など
- 遺言の有無 - 既存の遺言書や今後の作成予定
- 相続の考え方 - 兄弟間での分割方針や親の希望
特に子世代だけで決めず、「親が元気なうちに親の意向を聞く」ことが円滑な相続対策につながります。
名義変更・贈与・遺言・家族信託などの生前準備
実家の将来を左右する法的・税務的対策も押さえておきましょう。親が元気なうちに適切な準備をすることで、将来の手続きがスムーズになり、税負担も軽減できます。
📋 生前準備の4つの手法
不動産名義の確認・変更
実家の登記事項を確認し、生前贈与による名義変更を検討。年間110万円までは贈与税非課税です。
生前贈与
相続財産を減らして将来の相続税節税。相続時精算課税制度などの特例活用も可能です。
遺言書の作成
相続後の不動産処分方針を明確化。公正証書遺言が安全で、兄弟間トラブル防止に効果的です。
家族信託
親の認知症に備え、子に管理権を託す制度。迅速な処分・活用が可能で、成年後見より柔軟です。
📋 不動産名義の確認・変更のポイント
実家の登記事項(名義人)をまず確認します。相続で後から揉めないよう、生前に子ども名義へ移す選択肢もありますが、贈与税がかかるため注意が必要です。
💰 贈与税と相続登記の注意点
贈与税の基本
- 年間110万円まで非課税 - 暦年贈与課税の基礎控除
- 110万円超は高率贈与税 - 贈与額に応じて税率が上がる
- 住宅特例の注意 - 贈与後に親が介護施設へ入ると特例が受けられない場合も
相続登記の重要性
- 無登記のリスク - 固定資産税や借金の責任が残る可能性
- 早期手続きが重要 - 相続発生後は速やかに名義変更を
- 相続時精算課税制度 - 多額の不動産贈与を検討する場合の特例
📜 遺言書作成のメリットと方法
親が遺言書を作っておけば、相続後の不動産処分方針を明確化できます。特に兄弟が複数いる場合、遺言がないと法定相続分での共有が発生し、売却や管理の合意が難しくなる場合があります。
📝 遺言書の種類と特徴
公正証書遺言(推奨)
- 安全性が高い - 公証役場で作成、形式ミスによる無効リスクなし
- 確実な執行 - 公証人が関与するため法的効力が確実
- 紛失リスクなし - 原本は公証役場で保管
自筆証書遺言
- 手軽に作成 - 費用をかけずに自分で作成可能
- 形式ミスのリスク - 要件を満たさないと無効になる可能性
- 保管の問題 - 紛失や改ざんのリスクがある
🎯 遺言書で決めておくべき事項
- 誰が実家を引き継ぐか - 特定の子に相続させるか、共有にするか
- 売却益をどう分配するか - 売却する場合の代金分割方法
- 管理責任者の指定 - 空き家になった場合の管理担当者
- 処分方針の明示 - 売却・賃貸・取り壊しなどの方針
🤝 家族信託の活用メリット
親が認知症になる前に、親が財産管理できなくなったときに備え、信託契約で子どもに実家の管理権を託す方法です。これにより、将来親が施設入所などで判断能力を失っても、契約で決めた受託者(子)が不動産を管理・処分できます。
🚀 家族信託の大きなメリット
成年後見制度との比較
- 迅速な対応 - 成年後見は時間がかかるが、家族信託なら受託者の判断で迅速に売却・活用可能
- 柔軟な管理 - 契約内容に応じた自由度の高い財産管理が可能
- コスト効率 - 継続的な監督費用が不要
注意点と準備
- 認知症前の契約が必須 - 判断能力があるうちに制度利用開始が必要
- 専門家への相談 - 信託契約の作成には専門家の費用がかかる
- 税務申告の複雑化 - 通常より複雑な税務処理が必要(税理士相談推奨)
💰 売却時の税制特例
被相続人居住用財産の3,000万円控除
実家を「売却」する際には譲渡所得税の特例が使える場合があります。被相続人(親)の居住用財産を相続した子が2024年12月31日までに売却すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。例えば、相続した実家を売って資金化し介護費用に充てる際にも、この特例を活用すれば税負担が大幅に軽減できます。
実家の活用方法 - 売却・賃貸・管理・解体
親が入院・施設入所で実家が空き家になった時、どのような活用方法があるかを早めに検討しておきましょう。選択肢は主に住み続ける・売却・賃貸・管理・解体の5つです。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、家族にとって最適な方法を選択します。
🏠 実家活用の5つの選択肢
住み続ける
二世帯住宅化や同居で実家を活用。小規模宅地特例で相続時の土地評価を最大80%減額可能。
売却
現金化で管理負担なし。3000万円控除などの税制優遇を活用できれば税負担も軽減。
賃貸
家賃収入を得ながら資産保有。ただし借家人トラブルや修繕コスト、空室リスクに注意。
維持・管理
空き家バンク登録や管理サービス利用。月額数千円~数万円で遠方からでも管理可能。
解体・更地活用
老朽化建物を解体し、駐車場・資材置場として活用。資産価値低下を防止。
💡 選択の決め手となるポイント
- 親の意向・感情的価値 - 生家への愛着や近所づきあいなど
- 立地・築年数・建物状況 - 駅距離、築年数、修繕の必要性
- 家族の経済状況 - 維持費負担能力、相続税対策の必要性
- 市場動向 - 地域の不動産価格や需要の見通し
親が住み続けるためのリバースモーゲージ活用
親が「実家に住み続けたい」と希望する場合、リバースモーゲージを活用することで、実家を担保に老後資金を調達しながら住み続けることができます。これにより親のライフスタイルを変えることなく、貯蓄を温存して介護費用などに備えることが可能です。
💰 リバースモーゲージの仕組み
基本的な仕組み
- 自宅を担保に融資 - 実家を担保として金融機関から融資を受ける
- 住み続けながら資金調達 - 生存中は利息のみ支払い、元本は死亡時に住宅で返済
- 退職金の代替手段 - 一括または年金形式で資金を受け取り可能
- 配偶者も継続可能 - 配偶者がいる場合、配偶者も住み続けられる商品が多い
⚠️ リバースモーゲージの注意点
リスクと制約
- 長生きリスク - 想定よりも長期間利用すると借入限度額に達する可能性
- 金利リスク - 変動金利の場合、将来の金利上昇で返済総額が増加
- 担保評価の変動 - 不動産価格下落により借入限度額が減る可能性
- 審査・費用 - 物件評価や審査費用、保証料などの初期コスト
リバースモーゲージは複雑な金融商品のため、必ず複数の金融機関で比較検討し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
HomeLinQで安心・効率的な不動産査定・売却相談
実家の価値把握や売却を検討する際は、複数社での査定比較が重要です。HomeLinQは東京都心部を中心とした不動産プラットフォームで、無料査定・売却相談・買取見積が可能です。実家の活用方法を検討する上で、まずは市場価値を把握しておくことをおすすめします。
🏢 HomeLinQのサービス特徴
無料査定・買取見積
初期費用なしで不動産の適正価格を把握。近隣相場と比較した正確な査定を提供。
都内主要エリア対応
城南・城西・23区外エリアを中心に地域密着のサービス提供。市場動向に精通。
専門スタッフサポート
宅地建物取引士など不動産のプロが手続き相談からサポート。秘密厳守で安心。
📍 HomeLinQ対応エリア
城南エリア
- 港区
- 目黒区
- 品川区
城西エリア
- 新宿区
- 渋谷区
- 世田谷区
- 杉並区
- 中野区
23区外エリア
- 調布市
- 狛江市
- 三鷹市
🎯 HomeLinQの無料サービスを活用しよう
実家の生前対策を進める上で、まずは現在の市場価値を正確に把握することが大切です。HomeLinQの無料査定で、将来の計画立案にお役立てください。
※査定・相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ:実家を空き家にしないための総合戦略
実家を空き家にしないためには、親が元気なうちからの準備が何より重要です。家族間での話し合い、法的手続きの準備、活用方法の検討を通じて、将来のリスクを最小限に抑えることができます。
📝 生前対策の重要ポイント再確認
早期の家族話し合い
親の想いを尊重しつつ、協力的な姿勢で将来の方針を共有。お盆・正月などの機会を活用。
法的手続きの準備
遺言書・家族信託・生前贈与などで相続トラブルを事前に防止。専門家への相談も活用。
活用方法の検討
売却・賃貸・管理・住み続ける・解体の選択肢を家族の状況に応じて比較検討。
プロの活用
不動産会社・税理士・弁護士・司法書士など専門家との連携で安心の対策を実現。
🎯 今すぐ始められる3つのアクション
- 家族での話し合いを計画 - 次の帰省時やイベント時に話し合いの機会を設ける
- 実家の現在価値を把握 - HomeLinQなどで無料査定を行い、市場価値を確認
- 専門家の連絡先を確認 - 地域の司法書士・税理士・不動産会社の情報を収集
2033年には全住宅の3戸に1戸が空き家になる予測もあります。「まだ早い」ではなく「今こそ始めるタイミング」と考えて、家族みんなで安心の対策を進めましょう。