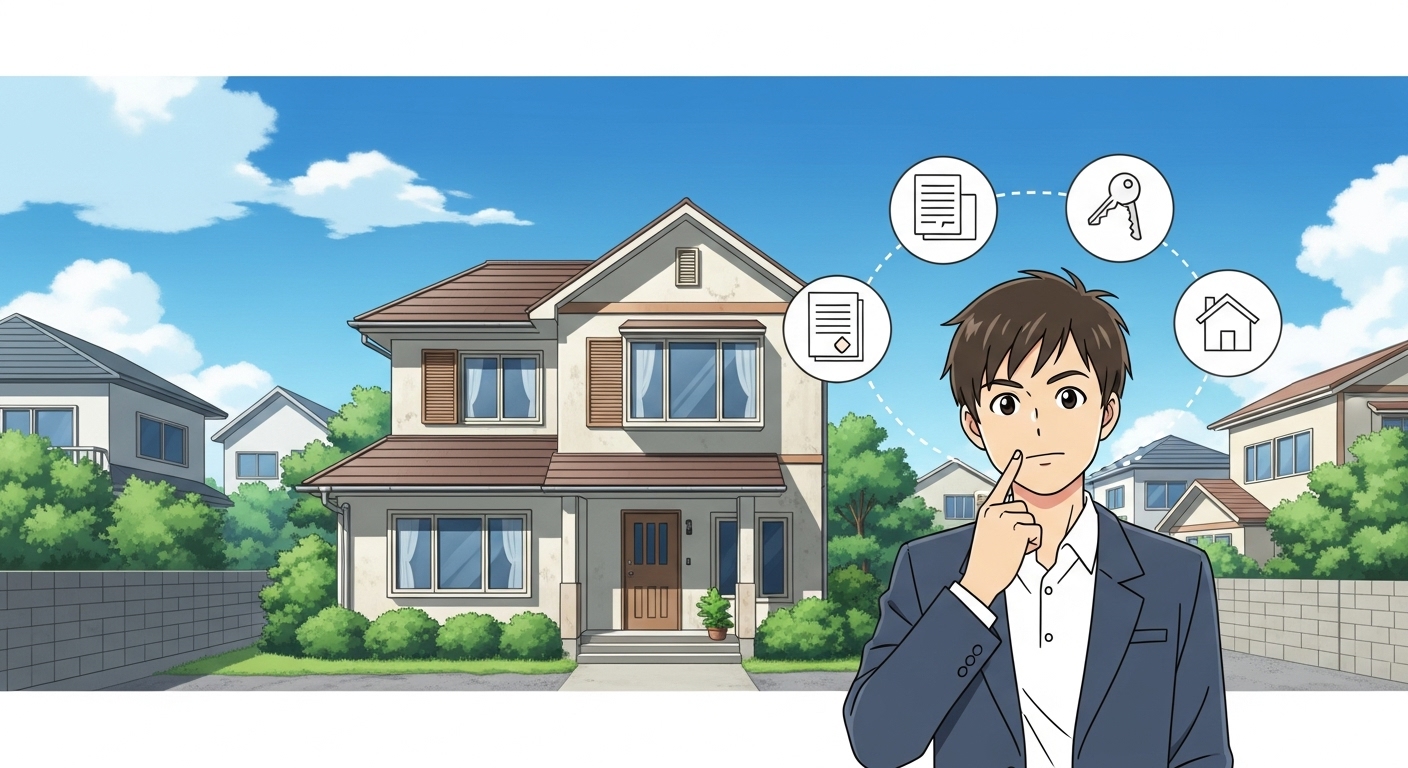
親や親族から急に実家を相続して空き家になってしまったとき、「まず何をしたらいいの?」と戸惑う方は少なくありません。愛着ある家だからこそ放置するのは心配ですし、かといって売るにも貸すにも具体的な手順がわからず不安になりますよね。実家を相続した直後には、法的な手続きや家の管理、活用方法の検討などやるべきことがいくつかあります。本ガイドでは、相続直後に必要な手続きや空き家を巡るリスク、そして「住む・貸す・売る」という3つの選択肢の比較ポイントを分かりやすく解説します。さらに、税制優遇や行政のサポート制度もうまく活用して、安心して実家を処分・活用するコツをご紹介します。
この記事でわかること
- 相続直後の必須手続き – 相続登記の義務化と法的手続きの進め方
- 空き家放置のリスク – 税負担増、維持コスト、防犯・近隣トラブルの実態
- 3つの活用選択肢 – 住む・貸す・売るのメリット・デメリット比較
- 遺品整理のコツ – 家族協力と効率的な片付け方法
- 税制優遇・サポート制度 – 空き家特例、自治体相談窓口の活用法
空き家問題は先送りにするほど複雑になります。正しい知識で早めの対策を取り、安心できる解決策を見つけましょう。
相続直後にまず行うべき手続き(相続登記の義務化など)
空き家を相続したら、なるべく早めに法的な手続きを済ませましょう。特に忘れてはいけないのが不動産の相続登記です。2024年(令和6年)4月から法律が改正され、不動産を相続した人は「その不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記を申請することが義務化されました。
⚠️ 相続登記義務化の重要ポイント
罰則と期限について
もし正当な理由もなくこの義務を怠ると、最大で10万円以下の過料(罰則金)が科される可能性があります。つまり、親名義だった実家の土地建物を相続した場合には、遅くとも3年以内に法務局で名義変更(相続登記)の申請を行う必要があるわけです。これは過去に相続した未登記の不動産にも適用され、既に相続して放置している分についても2027年3月末までに登記が必要とされています。
📋 相続登記の進め方
基本的な手続きの流れ
相続登記の手続きは、被相続人(亡くなった方)の戸籍収集や遺産分割協議書の作成など準備が必要です。自分で行うこともできますが、不安な場合は司法書士など専門家に相談するとスムーズです。2024年の法改正では「相続人申告登記」という簡易な方法も創設されましたが、基本的には正式な相続登記を完了させることが大切です。
最優先で取り組むべきステップ
まずは家族や相続人間で誰が不動産を相続するかを確定させ(遺産分割)、その上で必要書類を準備して登記申請を行いましょう。これが相続直後に最優先で取り組むべきステップです。相続登記を怠ると将来その不動産を売ることも難しくなりますし、罰則のリスクもありますので、早めに対応しましょう。
空き家を放置するとどうなる?考えられるリスク
大切な実家とはいえ、使う予定もない空き家をそのまま長期間放置すると様々な問題が生じます。何となく「空き家は良くない」と聞くけれど具体的に何がマズいのか、ここで押さえておきましょう。
⚠️ 空き家放置の4大リスク
税負担の急激な増加
管理不全の「特定空き家」に指定されると住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。空き家対策特別措置法の改正により課税強化される方向です。
維持管理コストの継続
雨漏り修繕・草木の剪定・防犯対策・火災保険料など、人が住んでいなくても維持費用はゼロにならないのです。誰も住まない家は想像以上に早く劣化が進みがちです。
防犯・防災上のリスク
空き家が犯罪の温床となるケースも指摘されています。放火・不法侵入・不法投棄の現場になったり、違法薬物製造に利用される事件も報道されています。
近隣トラブルと行政介入
管理されていない空き家は周囲の生活環境にも悪影響を及ぼします。雑草・害虫・倒壊リスクで近隣住民から損害賠償を請求される恐れや、行政による強制撤去もあります。
📊 具体的なリスク詳細
固定資産税の急増
家屋が建っている土地は住宅用地の特例で固定資産税が大幅に減額(標準課税の6分の1)されています。しかし老朽化などで管理不全の「特定空き家」に指定されると税の優遇措置が外れ、固定資産税が最大で6倍にも跳ね上がる可能性があります。何もせず放置すると税金面で大きな負担増となりかねません。
老朽化による修繕費増大
定期的な換気や清掃をしないと木材の腐食や害虫の発生が起こりやすく、後で活用しようと思ったときに修繕費用がかさむことになります。長く放置するほど余計な出費も増えるため、「そのうち何とかする」と先延ばしにするのは得策ではありません。
損害賠償リスク
実際に「隣の空き家から発生したシロアリ被害で自宅に損害が出た」「放置家屋が倒れてきそうで危ない」などの苦情は各地で増えています。最悪の場合、被害を受けた近隣住民から損害賠償を請求される事態にもなりかねません。また行政から空き家の所有者に対し改善勧告・命令が出され、強制的に撤去されるケースもあります(その費用は所有者負担になります)。
⚡ 重要な結論
放置はリスクだらけ
空き家をそのままにしておくことには「固定資産税の優遇がなくなり税金が上がる」「維持費ばかりかかる」「防犯上不安」「周囲にも迷惑をかける」などリスクだらけです。相続したものの今は使い道がないという場合でも、リスクヘッジのため適切に管理・整理しておくことが重要です。次章では、具体的に空き家をどう活用・処分するか考えるポイントを見ていきましょう。
空き家をどうする?「住む」「貸す」「売る」の選択肢を比較
使わなくなった実家については、大きく分けて「自分で住む」「誰かに貸す」「思い切って売る」の3つの選択肢があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、順番に見ていきましょう。
🏠 空き家活用の3つの選択肢
自分で住む
現在借家住まいであれば新たに家を買わずに済む大きなメリット。愛着のある実家に住み続けられる精神的な安心感もあります。リフォームや建て替えで快適に。
賃貸に出す
第三者に貸して家賃収入を得る方法。毎月安定した収入が入り、誰かが住んで管理してくれることで防犯上も安心。都心部や人気エリアなら需要が見込めます。
売却する
手放して現金化する最も現実的な選択肢。老朽化が進んだ家は早めに売却する方が有利。まとまった資金を得られ、維持管理の手間から解放されます。
選択肢1. 自分で住む場合(リフォーム・建て替えも検討)
相続した家に自分や家族が住む選択肢です。すでにマイホームを持っている場合は現実的ではないかもしれませんが、例えば現在借家住まいであれば新たに家を買わずに済むという大きなメリットがあります。愛着のある実家に住み続けられる精神的な安心感もあるでしょう。
🔨 住むための準備と検討事項
リフォーム・建て替えの検討
長年人が住んでいなかった家の場合、そのままでは生活するのが難しいケースも多いです。築年数が経っている家であればリフォームして住める状態にする、あるいは思い切って建て替えることも選択肢になります。リフォームなら思い出の家を活かしつつ必要な箇所を改修できますし、建て替えれば最新の耐震・省エネ住宅にできます。
重要な確認ポイント
自分で住む場合の注意点としては、その空き家が現在の建築基準法で建て替え可能かどうかも確認が必要です。「再建築不可物件」(道路幅などの要件を満たさず新築できない土地)だと、建て替えができません。リフォームで対応できるか、専門家に調査してもらうと安心です。また、遠方に住んでいる方が実家に移り住む場合は、生活拠点を移すことになるため家族の仕事や子供の学校など様々な調整が必要です。
選択肢2. 賃貸に出す場合(貸す選択肢)
自分たちは住まないが、家を手放すのも惜しい――そんな場合は第三者に貸して家賃収入を得るのも一つの方法です。空き家を賃貸物件にすれば、毎月安定した収入が入るメリットがありますし、誰かが住んで管理してくれることで防犯上も安心です。
💰 賃貸活用のメリット・デメリット
メリット
- 毎月の安定収入が得られる
- 誰かが住むことで防犯面でも安心
- 都心部や人気エリアなら需要が見込める
- 家を手放さずに済む
デメリット・注意点
- 古い家だと借り手が付きにくく、リフォームや設備交換が必要
- 家主(オーナー)としての責任が発生
- 入居者との契約手続き、家賃管理、設備故障時の対応が必要
- 将来的に売却しづらくなる可能性(オーナーチェンジ物件)
⚠️ 賃貸時の重要な注意点
将来の売却への影響
注意したいのは、将来的に売却しづらくなる可能性です。賃貸中の物件を途中で売ろうとしても、入居者がいる状態(オーナーチェンジ物件)だとマイホームとして購入したい人には売れず、投資用としてしか売却できなくなります。結果として買い手が限られ、売却価格が下がるケースもあります。一度貸すと「やっぱり売りたい」と思った時にハードルが上がる点には留意が必要です。
選択肢3. 売却する場合(専門家への相談も活用)
「住む予定もないし管理も大変、ならば手放して現金化する」という売却は、多くの空き家所有者が選択する現実的な選択肢です。特に老朽化が進んだ家だと年月とともに資産価値が下がるため、早めに売却してしまう方が有利な場合もあります。
💡 売却のメリットと税制優遇
売却の主なメリット
- まとまった資金を得られる - 生活費、教育費、新居購入の頭金に充当可能
- 維持管理の手間から解放 - 固定費や精神的な負担が軽くなる
- 早期売却で価値下落を防ぐ - 老朽化による資産価値減少を回避
空き家特例による大幅節税
売却時に覚えておきたいのが、「空き家特例」など税制上の優遇措置です。一定の条件を満たす空き家を相続し売却する場合、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円までを非課税にできる特別控除があります。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、2016年から始まった制度が現在2027年末まで延長されています。
📋 空き家特例の適用条件
主な適用要件
- 被相続人が一人で住んでいた家屋を相続した
- 1981年5月31日以前に建築された古い家屋である
- 相続後に誰も住まず事業にも使っていない
- 売却時に耐震リフォームまたは解体が完了している
該当すれば最大3000万円もの譲渡益が非課税になるため活用しない手はありません。例えば実家の売却益が2500万円出たとしても、この特例が使えればその全額が課税対象から外れるので大幅な節税になります。売却を検討する際は、事前に専門家や税務署等に相談してこの特例が使えるか確認しておきましょう。
🏗️ 売却方法の選択肢
仲介 vs 買取
空き家を売る方法としては、大きく「不動産会社に仲介を依頼して買い手を探す」か「不動産買取業者に直接買い取ってもらう」かの2種類があります。仲介なら市場価格で高く売れる期待がありますが時間がかかる場合もあります。買取ならば早く確実に現金化できますが相場より安くなる傾向があります。
古家付き vs 更地
空き家の状態によっては更地にして売った方が良いケースもあります。古家付きだと敬遠される場合や、更地にすると買い手が用途を自由に決められるため需要が高まる場合などです。解体費用と売却価格のバランスも踏まえて、不動産会社と相談しながらベストな売却方法を検討してください。
🎯 選択肢決定のポイント
空き家の活用には「住む・貸す・売る」の3つの選択肢があり、それぞれにメリットや注意点があります。管理や維持が難しいと感じる場合は、価値が下がる前に売却して費用負担を減らしつつ資金を得るのも賢明と言えるでしょう。ご自身やご家族の将来計画に応じて、最適な方法を選んでください。
家族・親族との相談と遺品整理のポイント
実家を相続したら、まずは家族や親族とよく話し合うことも重要です。特に複数の相続人がいる場合、今後その家をどうするか早めに意見をすり合わせておきましょう。「思い出があるから残したい」という感情もあれば、「維持が大変だから処分したい」という現実的な考えもあります。感情面と経済面の双方を考慮しつつ、家族全員が納得できる方向を探ることが大切です。
👨👩👧👦 家族との話し合いのポイント
感情面の配慮
「思い出があるから残したい」という気持ちは自然なもの。各人の想いを尊重しながら、現実的な解決策を模索することが大切です。
経済面の検討
維持費用・税金負担・修繕費など具体的な数字を共有し、「維持が大変だから処分したい」という現実的な判断も尊重します。
合意形成
意見が割れる場合は焦らず話し合いの場を持ち続けましょう。専門家を交えてファシリテーションしてもらうのも一案です。
遺品整理の進め方と注意点
話し合いと並行して進めたいのが、実家の片付け(遺品整理)です。親が長年暮らした家には大量の家具や思い出の品が残っているもの。いざ処分・活用するにしても、まずは中の荷物を整理しなくては始まりません。しかし遺品整理は想像以上に大仕事です。「物が多すぎてどこから手を付ければ…」と途方に暮れるケースも珍しくありません。
📦 効率的な遺品整理の5つのコツ
1. 皆で手分けして計画的に
相続人が自分一人ではないなら、兄弟姉妹など皆で協力して分担するのが基本です。一人で抱え込まず、「○月○日にはみんなで集まって○○を片付けよう」など日程と担当を決めて進めましょう。作業に区切りをつけ、「今日は押入れの中だけ片付ける」など1回ごとの目標量を決めて取り組むこともコツです。
2. 思い出に浸りすぎない
アルバムや手紙など思い出の品を整理していると、つい見入って手が止まってしまうものです。気持ちはよく分かりますが、作業中はあまり思い出に浸りすぎないよう意識することも大切です。貴重な写真などは手元に残しつつ、不要なものは思い切って処分するメリハリが必要でしょう。
3. 不用品は処分・リサイクル
何年も使っていない家具や衣類、大量の食器類など、この機会に整理します。使えそうな電化製品や家具はリサイクルショップに引き取ってもらったり、自治体の粗大ごみ回収を利用しましょう。重要書類や貴重品の見落としがないよう注意深くチェックすることもお忘れなく。預金通帳や権利証、保険証券など思わぬ場所から出てくることがあります。
4. 遠方在住・物が多すぎる場合は業者も活用
実家から離れて暮らしていて頻繁に通えない場合や、あまりに物が多く自力では難しい場合、専門の遺品整理業者に相談・依頼するのも手です。プロに任せれば短時間で一気に整理してくれますし、大型ごみの処理も代行してくれます。費用はかかりますが、自分たちではどうにもならないときは検討しましょう。自治体によっては遺品整理やごみ処分に関する助成制度がある場合もあります。
5. キレイに片付けておくメリット
将来的に実家を売却・賃貸・解体するにせよ、中の荷物をキレイに整理しておくことはプラスになります。例えば売却する場合、家の第一印象が良いかどうかで買い手の印象は大きく変わります。ガラクタだらけの家よりも、きれいに片付いていれば買主が「ここに住むイメージ」を抱きやすく、結果的に高く・早く売れる可能性も高まります。解体する場合でも、家財道具が残ったままだとゴミ処分費用が余計にかかるため、何もない状態まで整理してから解体した方が安く済むことが多いです。
⚡ 遺品整理で見つけておきたい重要書類
必須チェック項目
- 不動産関係:登記済権利証(権利書)、固定資産税納税通知書、測量図面
- 金融関係:預金通帳、キャッシュカード、証券類、保険証券
- 契約書類:住宅ローン契約書、リフォーム履歴、設備保証書
- その他重要書類:遺言書、エンディングノート、パスワード記録
🎯 遺品整理成功のポイント
遺品整理は手間と時間がかかりますが、家族で協力し計画的に進めれば必ず終わりが見えてきます。途中で疲れたら無理をせず休みつつ、少しずつでも前に進めていきましょう。どうしても進まない場合は行政のごみ相談窓口や専門業者の力も借りながら、実家を次のステップに進める準備を整えてください。
知っておきたい税制優遇や行政サポート制度
空き家を処分・活用する際には、税金面の優遇制度や自治体のサポートを知っておくと得をする場合があります。前述した「空き家特例(被相続人居住用財産の3000万円特別控除)」はその代表例ですが、それ以外にも押さえておきたい制度があります。
💰 主な税制優遇・サポート制度
空き家特例
相続した実家を売却時、条件を満たせば最高3000万円まで課税されない特例。2027年末まで延長され、大幅な節税メリットがあります。
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた土地を相続人が引き続き住む場合、相続税評価額を大幅に減額できる制度。相続税が大きく減免される可能性があります。
各種補助金
耐震リフォーム補助、除却(解体)費用の一部補助、空き家バンク利用者向けのリフォーム補助など。数十万円規模の補助が受けられることも。
固定資産税の軽減措置
老朽家屋を除却(解体)した土地に新たに住宅を建てる場合、一定期間固定資産税を減免する措置を講じている自治体もあります。
空き家特例による譲渡所得控除(詳細解説)
改めてになりますが、相続した実家を売却して譲渡益が出た場合、条件を満たせば最高3000万円まで課税されない特例があります。これはマイホームを売ったときの3000万円控除と同様に大きな節税メリットです。
📋 空き家特例の適用要件(詳細)
基本的な適用条件
- 被相続人が一人で住んでいた家屋を相続した
- 1981年5月31日以前に建築された古い家屋である
- 相続後に誰も住まず事業にも使っていない
- 売却時に耐震リフォームまたは解体が完了している
- 売却価格が1億円以下である
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
自治体発行の確認書が必要
適用期間は2027年末まで延長され、今後も延長・拡充の可能性があります。適用条件の確認や必要書類(自治体発行の確認書など)の取得が必要なので、売却前に必ずチェックしましょう。例えば世田谷区の場合、適用要件に合致するかを確認するための「被相続人居住用家屋等確認書」を区が発行しており、これがないと確定申告で特例を受けられません。各自治体の窓口で相談すれば教えてもらえます。
自治体や専門機関の相談窓口を活用しよう
空き家の処分・活用について悩んだとき、自治体や公的機関が設置している相談窓口を利用するのも非常に有効です。特に東京など都市部では、行政が民間業者と連携して空き家相談に乗ってくれる窓口があります。
🏛️ 官民連携の相談窓口例
世田谷区の取り組み
例えば東京都世田谷区では、官民連携の取り組みとして「せたがや空き家活用ナビ」という無料相談窓口を設置しています。ここでは空き家の専門アドバイザーが中立的な立場で、売却・賃貸だけでなく相続手続きや解体の相談まで含めて幅広く対応してくれます。所有者の悩みを丁寧に聞き取り、解決までの道筋を提案してくれる心強いサービスです。
全国展開の相談体制
さらに希望に応じて適切な事業者(不動産会社や管理業者など)を紹介してもらうことも可能で、複数業者を比較検討した上で選ぶこともできます。世田谷区以外でも、東京都内各区市や全国の自治体で似たような空き家相談窓口が開設されています。
🤝 NPO・協会などの民間サポート
専門団体の活用
公的機関以外にも空き家問題に取り組むNPOや協会などがあります。例えば「空き家管理士協会」や各地の「空き家バンク」運営団体などが情報提供や相談対応を行っています。東京なら「東京空き家相談センター」といった名称で民間団体が相談を受け付けているケースもあります。役所に相談するのはハードルが高いと感じる場合は、そうしたNPO等を利用するのも良いでしょう。
🔍 各種補助金・助成金の活用
国・自治体の補助制度
国や自治体では空き家対策の一環で様々な補助制度を用意しています。例えば耐震リフォーム補助や除却(解体)費用の一部補助、あるいは空き家バンク利用者向けのリフォーム補助などです。東京23区でも区ごとに制度が異なりますが、例えば大田区では老朽空き家除却費用の助成がありますし、世田谷区でも耐震改修やリフォームへの補助制度があります。
情報収集のコツ
条件に合えば数十万円規模の補助が受けられることもありますので、「空き家 自治体名 補助金」などで情報収集してみると良いでしょう。税金や費用面で有利になる制度は積極的に活用しましょう。「知らなかった…」ではもったいないので、少しでも得できるものは専門家に相談しつつ使うのがおすすめです。
🎯 専門家活用のポイント
重要なのは、一人で抱え込まず専門家に相談することです。法律手続きに強い弁護士・司法書士、税金に詳しい税理士、売却・活用プランを提案してくれる不動産会社やファイナンシャルプランナーなど、頼れるプロはたくさんいます。自治体の窓口を起点に必要に応じて各分野の専門家を紹介してもらえますので、「何から手を付けていいか分からない」状態であれば遠慮なく公的サービスを活用してください。
まとめ:安心して空き家を処分・活用するために
実家の空き家問題は、多くの人にとって人生で何度も経験することではありません。だからこそ戸惑いがちですが、ポイントさえ押さえれば安全かつ有利に処分・活用することは十分可能です。まずは相続登記など基本的な手続きを怠らずに行い、放置のリスクを認識した上で「住む・貸す・売る」の選択肢を冷静に比較しましょう。家族とよく話し合いながら遺品整理を進め、家の中も整理整頓して次のアクションに備えることが大切です。
🎯 空き家対策成功の5つのポイント
法的手続きの完了
相続登記の義務化対応と必要書類の整備
放置リスクの回避
税負担増・維持費・近隣トラブルの防止
最適な選択肢の選択
住む・貸す・売るの冷静な比較検討
税制優遇の活用
空き家特例・補助金・専門家相談の活用
家族との協力
遺品整理と将来計画の家族での話し合い
幸い、税制優遇や自治体の相談サービスなど使える制度や支援はたくさんあります。
不安なことは専門家に相談し、プロの知恵を借りることでベストな解決策が見えてくるでしょう。
もし「売却」という選択肢が少しでも頭にあるなら、早めに信頼できる不動産会社に査定や相談を依頼してみるのがおすすめです。
🏠 HomeLinQの空き家売却サポート
無料査定・相談
東京都・神奈川県エリアを中心に空き家となったご実家の無料査定・相談を承っています。市場動向に詳しいスタッフが現地を拝見し、今売るといくらになりそうか丁寧にご提案いたします。
売却から買取まで
売却以外に買取という方法も含めて最適なプランをご提案いたします。売却査定から買取のご提案までワンストップでサポートしておりますので、安心してご相談いただけます。
丁寧なサポート
大切な実家だからこそ、次の一歩は慎重に、しかし着実に踏み出しましょう。困ったときは早めの行動と相談が何よりの近道です。私たちも皆様のお力になれるよう全力でお手伝いいたします。
不要な空き家をそのまま抱えて悩み続けるよりも、ぜひ専門家に現状をお聞かせください。
もちろん査定は無料、ご相談だけでも歓迎です。
お気軽にお問い合わせください。