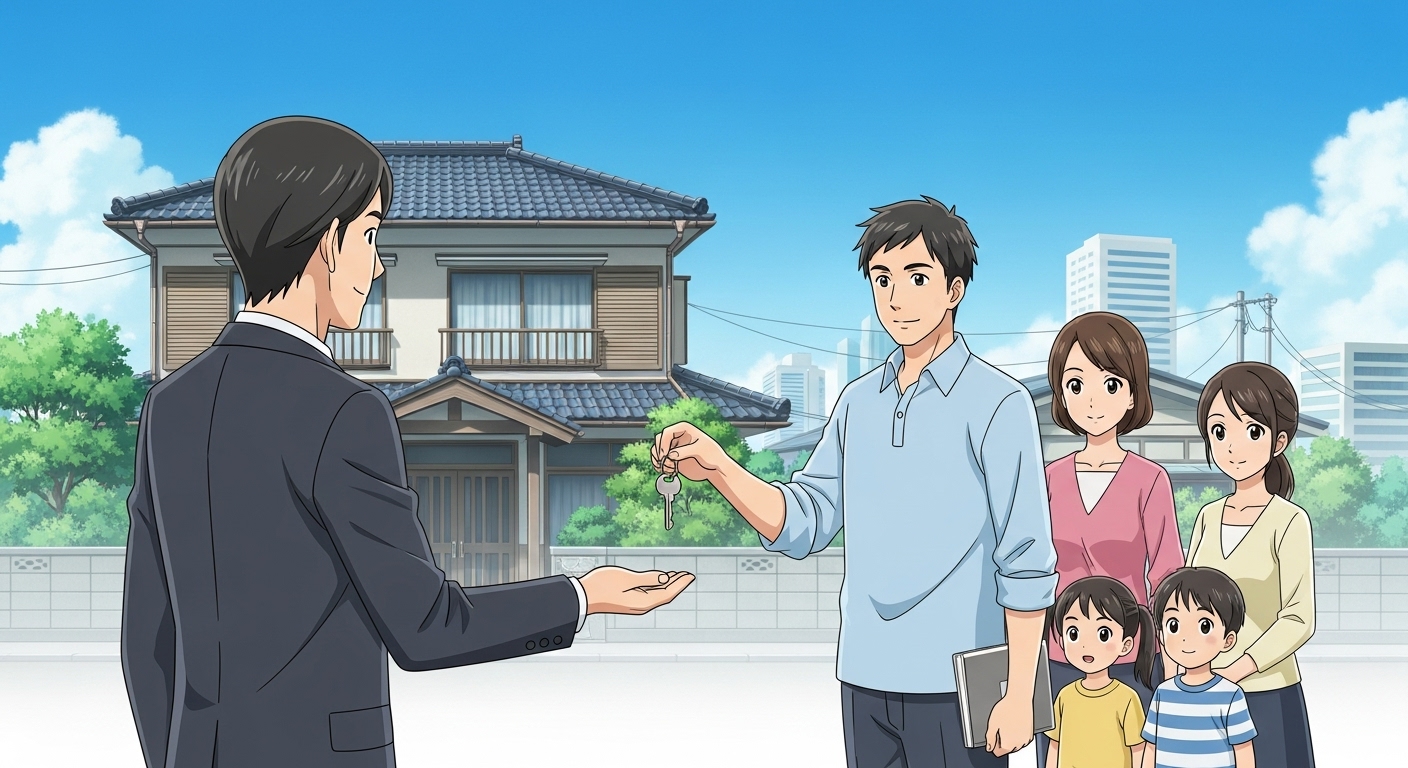
大切なご家族を亡くされた悲しみの中、突然直面する相続の手続き。「実家をどうしよう...」「手続きが複雑すぎて何から始めればいいの?」そんな不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。2024年から始まった相続登記の義務化や、複雑に見える税制も、正しい知識と適切なサポートがあれば、きっと乗り越えられます。このガイドでは、専門的な内容をわかりやすく・親しみやすく解説し、あなたの新しいスタートを全力でサポートします。
💙 多くの方が抱えるお悩み
何から始めればいいの?
「相続って聞いただけで難しそう...」
「手続きがたくさんあって混乱している」
→ 安心してください。段階的に丁寧にご案内します
期限が心配...
「3年以内って聞いたけど間に合う?」
「税金の申告期限はいつまで?」
→ 期限管理のコツもしっかりお教えします
家族との話し合いが...
「兄弟で意見が合わない」
「円満に解決したいけど...」
→ 家族の絆を大切にした解決方法をご提案
費用や税金が不安
「どのくらいお金がかかるの?」
「節税方法はあるの?」
→ 費用を抑える方法も含めて詳しく解説
🤝 このガイドがお約束すること
- 専門用語は使わず、わかりやすい言葉で説明
- お一人おひとりの心に寄り添ったサポート
- 最新の法改正・税制に完全対応
- 費用を最小限に抑える具体的な方法
- 信頼できる専門家との確実な連携
2024年から始まった相続登記の義務化って何?
まずは、簡単にご説明します
これまでは、相続で土地や建物を受け継いでも、「いつか手続きしよう」と後回しにしても特に問題はありませんでした。でも、2024年4月1日から法律が変わって、相続を知った日から3年以内に登記手続きをしないといけなくなったんです。
「えっ、3年しかないの?」と驚かれるかもしれませんが、大丈夫です。正しい順序で進めれば、きちんと期限内に完了できます。一緒に確認していきましょう。
なぜ義務化されたの?
実は日本では、「所有者不明土地」という問題が深刻化していたんです。
- 登記されていない土地が全国で410万ヘクタール(九州全体より広い!)
- 開発や災害復旧の妨げになっていた
- 空き家問題の原因にもなっていた
💡 つまり:相続登記の義務化は、日本全体の土地管理をきちんとするための大切な制度なんです。
具体的な期限と対象は?
期限について
- 2024年4月1日以降の相続
→ 相続を知った日から3年以内 - 2024年3月31日以前の相続
→ 2027年3月31日まで
✅ 過去の相続も猶予期間があるので安心!
対象となる財産
- 土地(宅地、農地、山林など)
- 建物(戸建て、マンション、店舗など)
- 共有持分も対象
💜 不動産の種類や価値に関係なく全て対象
もし期限を過ぎてしまったら...?
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
でも、ご安心ください
- 正当な理由があれば過料は科されません
- 売却予定であることも正当な理由になる場合があります
- 早めに専門家に相談すれば適切な対処法が見つかります
売却予定の方への特別なサポート
「売却するつもりだから、相続登記は必要ないのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、実は売却前に必ず相続登記が必要なんです。
HomeLinQならできること
- 相続登記と売却を同時進行でサポート
- 司法書士との連携でスムーズな手続き
- 費用を抑えた効率的なスケジュール提案
タイミングの最適化
- 相続登記から売却まで最短ルートをご提案
- 期限管理もしっかりサポート
- 税務申告のタイミング調整も安心
相続登記について理解できましたね!
次は、実際の売却手続きについて見ていきましょう 🏠
家族みんなで話し合おう!遺産分割協議書の作成
家族の絆を大切にした分割方法
相続した不動産を売却する時、相続人が複数いる場合は「みんなで納得のいく方法」を決める必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。
特に不動産を売却して現金で分ける「換価分割」という方法は、平等で納得しやすいので、多くのご家族に選ばれています。一緒に詳しく見ていきましょう。
3つの分割方法、どれがいい?
現物分割
不動産をそのまま相続人で分ける方法
👍 メリット:手続きが比較的簡単
👎 デメリット:不動産は分けにくく、価値が不平等になりがち
代償分割
一人が不動産を相続し、他の相続人に現金を支払う方法
👍 メリット:不動産を残せる
👎 デメリット:まとまった現金が必要
換価分割
不動産を売却して、現金を相続人で分ける方法
👍 メリット:平等で公平、管理の手間がない
👍 その他:現金化で他の用途にも使いやすい
換価分割が選ばれる理由
平等性
- 売却金額を法定相続分または話し合いで決めた割合で分配
- 「あの人ばかり得をしている」という不満が起きにくい
- 兄弟姉妹の関係が悪化するリスクを軽減
実用性
- 維持管理の負担から解放される
- 固定資産税などのランニングコストがかからない
- 将来の価値下落リスクを回避
心理的負担の軽減
- 「実家を手放すのは忍びない」という気持ちを家族で共有
- 一人だけが重い責任を負わなくて済む
- みんなで決めた結果なので後悔が少ない
遺産分割協議書、こうやって作ります
相続人全員で話し合い
「実家を売却して、みんなで分けよう」という方針を確認。売却価格の分配割合も決めておきます。
代表者を決める
売却手続きを進める代表者(通常は1名)を決めます。一旦この方の名義で相続登記を行います。
協議書に記載する内容
- 換価分割を行うことを明記
- 代表者が売却手続きを行うことを記載
- 売却代金の分配割合を具体的に記載
- 売却費用の負担方法も決めておく
署名・押印
相続人全員が署名し、実印で押印。印鑑証明書も添付します。
うまくいくためのコツと注意点
話し合いのコツ
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- 全員が納得できるまで時間をかける
- 必要に応じて専門家にも相談
トラブル予防
- 売却価格の査定は複数社で実施
- 費用の内訳も事前に確認
- 売却時期についても合意形成
HomeLinQが提携している不動産会社がお手伝いできること
協議書作成サポート
司法書士と連携して、法的に適切な協議書の作成をサポート
売却価格の適正査定
複数の査定方法で公正な価格を算出し、ご家族全員に提示
家族会議のファシリテート
中立的な立場から、円滑な話し合いをサポート
家族での話し合い方法が分かりましたね!
次は、相続人みんなで合意を形成するコツを見ていきましょう 👨👩👧👦
みんなが納得!相続人同士の上手な話し合い方
家族だからこそ、大切にしたい話し合い
相続の話し合いは、「お金のことだから」と言って避けがちですが、実は家族の絆を深める大切な機会でもあります。お互いの気持ちを理解し合い、みんなが笑顔になれる解決策を見つけましょう。
ここでは、相続人同士が気持ちよく話し合える方法と、よくある「もめごと」を事前に防ぐコツをご紹介します。
話し合いの基本姿勢:まずはお互いを思いやる心から
故人への感謝を共有
まずは「お父さん(お母さん)のおかげで今があること」を家族みんなで確認し合いましょう。
💡 例:「お父さんが大切に守ってくれた家を、みんなで大切にしていこうね」
みんなの意見を大切に
年上だから、長男だからという理由で決めず、相続人全員の気持ちを聞きましょう。
💡 例:「○○ちゃんはどう思う?」と一人ひとりに声をかける
急がず、焦らず
「今日中に決めなくても大丈夫」という気持ちで。時間をかけて納得のいく結論を出しましょう。
💡 例:「また来週、みんなで話し合いましょう」
効果的な話し合いの進め方(ステップ別)
情報共有フェーズ
- 不動産の現況を全員で確認(場所、状態、築年数など)
- 相続登記の期限や必要な手続きの説明
- 売却した場合の想定価格を複数社から聞いてみる
- 税金や費用についても大まかに把握
気持ちの共有フェーズ
- 「実家への思い」を一人ずつ話してもらう
- 「理想的な解決策」を自由に発言
- 心配事や不安も素直に共有
- この段階では否定せず、まずは聞くことが大切
選択肢の検討フェーズ
- 現物分割・代償分割・換価分割のメリット・デメリット比較
- 「もし売却するなら」の具体的な手順と期間
- 「もし誰かが住み続けるなら」の現実的な負担
- 複数のパターンでシミュレーション
合意形成フェーズ
- 全員が納得できる方法を徐々に絞り込む
- 「Win-Win」になる解決策を模索
- 詳細な条件(分配割合、手続き分担など)を決定
- 遺産分割協議書の内容を最終確認
よくある意見の対立と、上手な解決方法
「実家を手放したくない」vs「早く売却したい」
解決のアプローチ
- 「なぜ手放したくないのか」の理由を深く聞く(思い出、将来の計画など)
- 「なぜ早く売りたいのか」の事情も理解する(経済的事情、管理負担など)
- 中間案を検討:「1年間だけ様子を見て、その後売却」など
- 思い出の品は売却前にきちんと整理・分配
「法定相続分で」vs「貢献度を考慮して」
解決のアプローチ
- 「介護や世話の負担」を具体的に整理・確認
- 「経済的な貢献」(家のリフォーム代負担など)も考慮
- 数字だけでなく、感謝の気持ちも表現する
- 必要に応じて専門家に中立的な意見を求める
「高く売りたい」vs「早く売りたい」
解決のアプローチ
- 市場価格の調査を複数社で実施し、現実的な価格帯を把握
- 「○ヶ月以内に○○万円以上で売れなかったら値下げ」などの条件設定
- 維持費用(税金、管理費など)も売却期間と合わせて計算
- 「早期売却ボーナス」「高値売却ボーナス」の分配方法も検討
感情的にならないための「心の準備」
一息つく習慣
- 熱くなったら「ちょっと休憩」を提案
- お茶を飲むなど、リラックスタイム
- 「今日はここまで」と区切る勇気
言葉選びの工夫
- 「でも」「しかし」ではなく「そうですね、そして」
- 「○○さんの気持ちもわかります」を先に言う
- 「みんなのために」を主語にする
客観的な視点
- 「もし故人が生きていたら」と考えてみる
- 数字やデータを活用した判断
- 第三者の意見も参考にする
HomeLinQが提携している不動産会社がお手伝い「家族会議サポート」
「家族だけでは話し合いが進まない...」
そんな時は、HomeLinQの専門スタッフが中立的な立場で話し合いをサポートします。
話し合いの進行
感情的にならないよう配慮しながら、建設的な議論をサポート
データに基づく提案
市場価格や税金計算など、客観的な情報を提供
心理的なケア
家族それぞれの想いを大切にしながら、最適解を一緒に見つけます
家族会議サポートも無料相談の対象です。
お気軽にご相談ください。
家族での合意形成のコツが分かりましたね!
次は、具体的な売却費用について詳しく見ていきましょう 💰
しっかり把握!相続不動産売却にかかる費用の全て【2025年版】
費用を知って、安心して売却計画を立てよう
「売却にどのくらい費用がかかるの?」というのは、みなさんが最初に気になる点ですよね。しっかりと費用を把握しておけば、手元に残る金額も正確に計算でき、家族での話し合いもスムーズに進みます。
ここでは、相続不動産の売却にかかる全ての費用を、2025年最新版の税制・手数料に基づいて詳しくご説明します。「こんな費用もあったの?」という驚きがないよう、しっかりとチェックしていきましょう。
売却費用の全体像:大きく分けて4つのカテゴリ
登記関連費用
相続登記・抵当権抹消
目安:10~20万円
仲介関連費用
仲介手数料・広告費用
目安:売却価格の3~4%
税金
譲渡所得税・住民税
利益の20.315%または39.63%
その他費用
測量・解体・清掃等
物件により大きく変動
1. 登記関連費用の詳細
相続登記費用
登録免許税
- 固定資産税評価額の0.4%
- 例:評価額2,000万円 → 8万円
- 2025年3月31日まで軽減税率適用
司法書士報酬
- 5~10万円(一般的な相場)
- 相続人数や物件数により変動
- 戸籍収集代行も含む場合あり
必要書類取得費
- 1~3万円程度
- 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書等
- 相続人数により変動
抵当権抹消費用(該当する場合)
登録免許税:不動産1個につき1,000円
司法書士報酬:2~5万円
合計目安:3~6万円
2. 仲介関連費用の詳細
仲介手数料の計算方法
法定上限額(2025年現在)
- 200万円以下の部分:5% + 消費税
- 200万円超400万円以下の部分:4% + 消費税
- 400万円超の部分:3% + 消費税
簡単計算式(400万円超の場合)
仲介手数料 = (売却価格 × 3% + 6万円)× 1.1
売却価格2,000万円の場合
仲介手数料:72.6万円
売却価格3,000万円の場合
仲介手数料:105.6万円
売却価格5,000万円の場合
仲介手数料:171.6万円
その他の仲介関連費用
広告・宣伝費
- 基本的には仲介会社負担
- 特別な広告は別途費用の場合も
- 事前に確認が重要
ハウスクリーニング
- 5~15万円程度
- 売却前の印象アップに効果的
- 必須ではないが推奨
ホームステージング
- 10~30万円程度
- 空き家の場合に効果的
- 早期・高値売却が期待できる
3. 税金の詳細(2025年版)
譲渡所得税・住民税の計算の仕組み
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
取得費
- 購入時の価格
- 改良費(リフォーム等)
- 購入時の諸費用
- 不明な場合:売却価格の5%
譲渡費用
- 仲介手数料
- 印紙税
- 測量費
- 解体費等
税率(2025年現在)
短期譲渡所得(5年以下)
39.63%
所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%
長期譲渡所得(5年超)
20.315%
所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%
所有期間は取得した日から売却した年の1月1日までで判定
費用を上手に抑える5つのポイント
複数社で見積もり比較
- 仲介手数料の交渉
- 司法書士報酬の比較
- リフォーム業者の相見積もり
タイミングの最適化
- 長期譲渡所得の適用を狙う
- 特別控除の併用
- 市場動向を見極めた売り時
一括サービスの活用
- 相続登記から売却まで一貫サポート
- 専門家間の連携で重複費用削減
- パッケージ料金での割引
書類の事前準備
- 戸籍等は自分で取得
- 購入時の書類整理
- 改良履歴の記録整備
正確な費用試算
- 隠れた費用も含めて計算
- 税制特例の活用検討
- 手元に残る金額を明確化
売却費用がしっかり分かりましたね!
次は、手続きに必要な書類について確認していきましょう 📋
これで完璧!必要書類の完全チェックリスト【2025年版】
書類集めも、一歩ずつ確実に
「必要な書類がたくさんありすぎて...」と感じる方も多いですが、安心してください。必要な書類は取得する順番とタイミングが分かれば、効率よく集められます。
このチェックリストでは、どこで・いくらで・どのタイミングで書類を取得すれば良いのかを、わかりやすく整理してご案内します。手続きごとに分けて説明しているので、「今、何が必要?」がすぐにわかります。
書類の全体像:3つの手続き段階別
相続関係確定
相続人調査・財産調査
期間:1~2ヶ月
登記・分割協議
相続登記・協議書作成
期間:1~2ヶ月
売却・税務申告
売買契約・確定申告
期間:3~6ヶ月
フェーズ1:相続関係確定の書類
相続人確定関係書類
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
取得場所:本籍地の市区町村役場
費用:1通450円
期間:郵送の場合1~2週間
💡 転籍がある場合は、転籍前の市区町村からも取得が必要
相続人全員の戸籍謄本
取得場所:各相続人の本籍地
費用:1通450円
有効期限:発行から3ヶ月以内
💡 被相続人との関係を証明するため
被相続人の住民票除票
取得場所:最後の住所地の市区町村
費用:1通300円
注意:本籍地記載のものを取得
💡 戸籍と住民票で同一人物であることを証明
相続人全員の住民票
取得場所:各相続人の住所地
費用:1通300円
有効期限:発行から3ヶ月以内
💡 現在の住所を証明するため
財産調査関係書類
固定資産評価証明書
取得場所:不動産所在地の市区町村
費用:1通300~400円
用途:登録免許税計算
登記事項証明書(全部事項)
取得場所:法務局(オンライン可)
費用:1通600円(オンライン500円)
用途:現在の所有者確認
権利証・登記識別情報
保管場所:被相続人の自宅等
費用:なし
注意:紛失時は別途手続きが必要
フェーズ2:登記・分割協議の書類
相続登記関係書類
遺産分割協議書
作成者:相続人全員で協議して作成
費用:なし(司法書士依頼時は別途)
注意:相続人全員の署名・実印必要
相続人全員の印鑑証明書
取得場所:各相続人の住所地
費用:1通300円
有効期限:発行から3ヶ月以内
登記申請書
作成者:申請人(通常は司法書士)
費用:なし
注意:法務局指定の書式を使用
売却準備関係書類
建物図面・測量図
取得場所:法務局
費用:1通500円
用途:売却時の物件資料
境界確定書・測量書
作成者:土地家屋調査士
費用:30~100万円
期間:3~6ヶ月
フェーズ3:売却・税務申告の書類
売買契約関係書類
売買契約書
作成者:仲介業者
費用:印紙税(1~6万円)
注意:売主・買主が各1通保管
重要事項説明書
作成者:宅地建物取引士
費用:なし
用途:物件の重要事項を説明
売主の本人確認書類
内容:運転免許証・パスポート等
費用:なし
注意:有効期限内のもの
確定申告関係書類
売買契約書(写し)
用途:売却価格・諸費用の証明
保管期間:申告から7年間
注意:税務署提出用
取得時の契約書・領収書
用途:取得費の証明
注意:不明な場合は売却価格の5%
探し方:自宅・銀行・不動産会社
改良費の領収書
内容:リフォーム・修繕費用
用途:取得費加算
注意:修繕費は対象外の場合も
書類取得の効率的な順序とコツ
まずは戸籍調査から
- 被相続人の戸籍を出生から死亡まで取得
- 転籍履歴も漏れなく確認
- 相続人の範囲を確定
相続人全員の書類
- 戸籍謄本・住民票を同時取得
- 有効期限(3ヶ月)に注意
- 印鑑証明書は協議成立後に取得
不動産関係書類
- 登記事項証明書で現況確認
- 固定資産評価証明書で評価額確認
- オンライン取得で時間短縮
費用節約のコツ
- まとめて取得で交通費節約
- 郵送申請も活用
- コンビニ交付対応地域では利用
HomeLinQ提携不動産会社が主導する「書類取得代行サービス」
「書類集めが大変で時間がない...」
そんな方のために、HomeLinQの提携不動産会社の関連機関と連携し、
書類取得から売却完了まで、ワンストップでサポートします。
書類取得代行
戸籍収集から登記書類まで、専門スタッフが代行取得
時間短縮
通常1~2ヶ月かかる作業を専門家ネットワークで迅速化
確実性
書類の不備や期限切れを防ぐプロフェッショナル対応
お気軽にお問い合わせください。
必要書類がよく分かりましたね!
次は、税務申告の流れとタイミングについて確認していきましょう 📊
安心して進める!税務申告の流れとタイミング【2025年版】
税務申告も、正しい順序で進めれば大丈夫
「税金の手続きは難しそう...」と不安に思う方も多いですが、相続不動産の売却に関する税務申告は、適切なタイミングとステップを知っていれば、決して怖いものではありません。
ここでは、いつまでに・何を・どのように申告すれば良いのかを、2025年最新版の税制に基づいて分かりやすく解説します。期限管理から節税ポイントまで、一歩ずつ確実に進められるガイドです。
税務申告の全体スケジュール:重要な期限を確認
売却完了~年末まで
- 売却必要書類の整理(契約書、領収書等)
- 取得費証明書類の収集(購入時契約書等)
- 特別控除適用可否の確認
- 概算税額の計算(専門家相談推奨)
申告書作成準備期間
- 必要書類の最終確認
- 譲渡所得税の正確な計算
- 確定申告書の作成
- 税理士との打合せ(必要に応じて)
確定申告期限(厳守!)
- 税務署への申告書提出
- 納税手続き(口座振替は4月中旬)
- 特別控除等の特例適用申請
この期限を過ぎると、加算税・延滞税が発生します
申告が必要?不要?判断基準を明確に
申告が必要なケース
譲渡益が発生した場合
売却価格 > (取得費 + 譲渡費用)
→ 必ず申告・納税が必要
特別控除を適用する場合
損失でも申告が必要
3,000万円控除、軽減税率等を適用
損失を繰越したい場合
譲渡損失の損益通算・繰越控除
→ 将来の節税効果を得るため
申告が不要なケース
単純な譲渡損失
売却価格 < (取得費 + 譲渡費用)
かつ特例適用を希望しない場合
非課税範囲内の売却
生活用動産の売却
(日常生活で使用していた家具等)
注意事項
判断に迷ったら専門家に相談
後から追徴課税されるリスクを回避
申告書作成の流れ:ステップバイステップガイド
譲渡所得の計算
必要な数字を整理
- 売却価格(手取り金額)
- 取得費(購入価格+諸費用)
- 譲渡費用(仲介手数料等)
計算式の適用
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
特別控除の適用検討
主な特別控除
- 3,000万円の特別控除
- 軽減税率の特例
- 買換えの特例
適用要件の確認
各特例の要件を詳細に確認
(居住年数、面積要件等)
税額の計算
税率の確認
- 短期譲渡:39.63%
- 長期譲渡:20.315%
- 軽減税率:14.21%(一部)
最終税額の算出
課税対象額 × 税率 = 納税額
申告書の作成・提出
必要な申告書
- 確定申告書B第一表・第二表
- 申告書第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書
提出方法
税務署窓口・郵送・e-Tax
期限:3月15日(厳守)
期限管理のポイント:遅れると大きなペナルティ
申告期限を過ぎた場合
- 無申告加算税:最大20%
- 延滞税:年7.3%~14.6%
- 特別控除の適用不可
納税期限を過ぎた場合
- 延滞税が日割りで発生
- 督促状の送付
- 差押えの可能性
対策・予防方法
- 売却後すぐに準備開始
- 税理士への早期相談
- 書類の事前整理
💡 おすすめ:売却完了後、できるだけ早く専門家に相談しましょう
HomeLinQ「税務申告安心サポート」
「税務申告って難しそう...間違えたらどうしよう」
そんな不安を解消するため、HomeLinQでは税理士との連携サポートを提供しています。
専門税理士紹介
不動産売却に精通した税理士をご紹介、安心の専門対応
申告書作成代行
複雑な計算から申告書作成まで、プロが全てサポート
節税対策提案
最適な特例適用で、税負担を最小限に抑制
税務申告サポートも無料相談で承ります。
売却前の税額シミュレーションも可能です。
税務申告の流れがわかりましたね!
次は、節税につながる特例制度について詳しく見ていきましょう 💰
大幅節税を実現!特例制度の活用戦略【2025年版】
知らないと損する!使える特例制度を最大限活用
相続不動産の売却では、適切な特例制度を活用することで数百万円以上の節税が可能です。「知らなかった」「申告期限に間に合わなかった」で損をしないよう、利用できる制度を確実にチェックしましょう。
ここでは、2025年最新版の税制に基づき、相続不動産売却で活用できる主要な特例制度と、その上手な組み合わせ方を詳しく解説します。あなたのケースに最適な節税戦略を見つけましょう。
特例制度の全体マップ:あなたに使える制度はどれ?
居住用財産関連
- 3,000万円の特別控除
- 軽減税率の特例
- 買換えの特例
- 譲渡損失の繰越控除
💡 被相続人が住んでいた家の売却で活用
空き家関連
- 空き家の3,000万円控除
- 取得費加算の特例
- 相続税の取得費加算
💡 相続後に空き家となった物件で活用
一般的な特例
- 長期譲渡所得の軽減税率
- 5年ルールの活用
- 取得費の特例
💡 すべての不動産売却で基本となる制度
最強の節税効果!3,000万円の特別控除
制度の概要と節税効果
基本的な仕組み
居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度。
相続した実家の売却でも適用可能。
節税効果の例
譲渡益が3,000万円以下 → 税額ゼロ
譲渡益が5,000万円 → 約406万円の節税
(長期譲渡20.315%の場合)
適用要件をクリアして確実に控除を受ける
物件要件
- 被相続人の居住用財産であること
- 家屋の床面積が50㎡以上
- 昭和56年5月31日以前建築は耐震基準適合
- 相続開始直前に被相続人以外居住していない
期限要件
- 相続開始日から3年後の12月31日までに売却
- 売却年の翌年3月15日までに確定申告
- 2027年12月31日までの特例措置
相続人要件
- 相続により取得した相続人が売却
- 相続開始直前に同居していない
- 相続開始前3年以内に特例適用なし
売却要件
- 親族以外への売却
- 売却価格が1億円以下
- 家屋は取壊しまたは耐震リフォーム済み
見落としがちな注意点と対策
耐震基準適合証明
昭和56年以前の建物は耐震診断が必要。
解体する場合は解体後の土地のみ売却。
3年以内売却
相続開始から3年後の年末が期限。
早めの売却活動開始が重要。
他の特例との併用
軽減税率との併用可能。
相続税の取得費加算も併用検討。
10年超所有で税率が大幅軽減!軽減税率の特例
制度の概要
所有期間10年超の居住用財産を売却する場合、6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
💡 3,000万円控除と併用可能!
控除後の残額に軽減税率を適用
税率比較
通常の長期譲渡
20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興税0.315%)
軽減税率(6,000万円以下)
14.21%(所得税10% + 住民税4% + 復興税0.21%)
節税効果:約6%の税率軽減
適用要件
- 所有期間が10年超(相続の場合は被相続人の所有期間通算)
- 居住用財産の売却
- 売却年の前年及び前々年に適用を受けていない
- 3,000万円控除と併用可能
活用例
売却価格:8,000万円、取得費:2,000万円
① 譲渡所得:6,000万円
② 3,000万円控除適用:3,000万円
③ 軽減税率適用:3,000万円 × 14.21% = 426万円
通常税率なら609万円 → 183万円の節税!
空き家問題解決と節税の両立!空き家の3,000万円控除
空き家特例の概要
制度の目的
空き家の発生を抑制し、適切な管理・活用を促進するため、一定の要件を満たす空き家の売却について3,000万円の特別控除を適用。
適用期間
2023年12月31日まで延長
(当初2019年末期限から延長)
さらなる延長の可能性も
適用要件の詳細チェック
建物要件
- 昭和56年5月31日以前に建築
- 区分所有建物以外(戸建て住宅等)
- 相続開始直前に被相続人以外居住せず
- 相続開始直前に事業・貸付・居住用でない
売却時要件
- 耐震リフォーム実施または家屋除却後の売却
- 相続時から売却時まで事業・貸付・居住用でない
- 売却価格が1億円以下
- 親族以外への売却
期限要件
- 相続開始日から3年後の12月31日までに売却
- 2023年12月31日までに売却
- 確定申告期限内に申告
実務上の重要ポイント
耐震リフォーム vs 解体
解体の方が一般的。耐震リフォームは費用対効果を慎重に検討。
居住用財産特例との選択
どちらか一方のみ適用。有利な方を選択する必要あり。
必要書類の事前準備
被相続人居住用家屋等確認書など、市区町村での手続きが必要。
相続税を節税に活用!取得費加算の特例
制度の仕組み
相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算できる制度。譲渡所得が減り、税負担が軽減されます。
取得費 = 本来の取得費 + 加算される相続税額
加算額の計算式
加算額 = 相続税額 × (売却不動産価額 ÷ 相続財産価額)
- 相続税額:相続人が実際に支払った税額
- 売却不動産価額:相続税評価額
- 相続財産価額:相続税の課税価格の計算基礎
適用要件
- 相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却
- 相続税を実際に支払っている
- 相続により取得した財産の売却
- 他の特例制度と併用可能
節税効果の例
相続税額:1,000万円、不動産割合:50%
加算額:1,000万円 × 50% = 500万円
譲渡所得の減少:500万円
節税効果:500万円 × 20.315% = 約102万円
最大効果を狙う!特例の組み合わせ戦略
最強の組み合わせ
3,000万円控除 + 軽減税率 + 取得費加算
- 10年超所有の居住用財産
- 相続税の支払いあり
- 最大の節税効果を実現
空き家の場合
空き家3,000万円控除 + 取得費加算
- 昭和56年以前の建物
- 解体または耐震リフォーム
- 2023年末までの売却
慎重な選択が必要
居住用 vs 空き家特例
- どちらか一方のみ適用
- 軽減税率の有無で判断
- 専門家による試算推奨
💡 重要:特例選択は売却前の事前検討が必須です
HomeLinQ提携不動産会社が主導する「節税コンサルティング」
「どの特例を使えば一番お得?」「組み合わせ方が分からない」
そんな疑問にお答えするため、HomeLinQでは個別の節税コンサルティングを提供しています。
特例適用シミュレーション
複数パターンの税額計算で最適な特例組み合わせを提案
タイミング戦略
売却時期の最適化で長期譲渡・特例期限を有効活用
申告サポート
確定申告書の作成から提出まで、税理士と連携してフルサポート
節税コンサルティングも無料相談から始められます。
まずはお気軽にご相談ください。
節税特例がよく分かりましたね!
次は、全体の流れを整理したタイムラインを確認していきましょう ⏰
全体の流れが一目瞭然!相続から売却完了までのタイムライン【2025年版】
迷わず進める!全体の流れとタイミングを把握
相続不動産の売却は多くの手続きと期限があり、「何から始めれば良いの?」「いつまでに何をすれば?」と戸惑う方が多いです。でも安心してください。
ここでは、相続発生から売却完了・税務申告までの全体的な流れを、具体的な期間とポイントとともに整理しました。このロードマップに沿って進めれば、スムーズに売却を完了できます。
全体期間の概要:計画的に進めよう
標準的なケース
- 相続人が少数
- 争いなし
- 書類が揃っている
- 特例制度を活用
複雑なケース
- 相続人が多数
- 意見調整が必要
- 書類収集に時間
- 境界確定が必要
トラブルケース
- 相続争い発生
- 調停・審判
- 複雑な権利関係
- 専門家必須
💡 重要な期限:相続開始から3年以内(特例制度適用のため)
詳細タイムライン:段階別の進め方
相続発生~3ヶ月
基礎固めの期間
相続の基本手続きと情報収集を行う重要な期間。この段階での準備が後の進行をスムーズにします。
相続発生~2週間
- 死亡届の提出(7日以内)
- 遺言書の確認
- 相続人の概算把握
- 重要書類の保全
- 葬儀・法要の準備
2週間~1ヶ月
- 相続人調査の開始
- 財産調査の開始
- 不動産の現況確認
- 専門家への相談検討
- 関係者への連絡
1~3ヶ月
- 戸籍収集の完了
- 財産目録の作成
- 相続放棄の判断(3ヶ月以内)
- 相続人間の意向確認
- 売却方針の検討開始
3ヶ月~6ヶ月
協議・準備の期間
遺産分割協議と売却準備を並行して進める期間。合意形成と具体的な準備作業が中心になります。
3~4ヶ月
- 遺産分割協議の開始
- 不動産の査定依頼
- 売却方針の決定
- 税理士・司法書士の選定
- 相続税申告の検討
4~5ヶ月
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産会社の選定
- 特例制度の適用検討
- 売却準備の開始
- 必要書類の収集
5~6ヶ月
- 相続登記の申請
- 媒介契約の締結
- 物件の整理・清掃
- 境界確定(必要に応じて)
- 売却活動の開始
6ヶ月~1年
売却実行の期間
実際の売却活動から契約・決済まで。適切な価格設定と販売戦略で早期売却を目指します。
6~8ヶ月
- 本格的な売却活動
- 内覧対応・条件交渉
- 価格調整の検討
- 購入申込の受付
- 売買条件の調整
8~10ヶ月
- 売買契約の締結
- 決済準備の開始
- 住宅ローン手続き(買主)
- 税理士との打合せ
- 特例適用書類の準備
10~12ヶ月
- 最終決済・引渡し
- 所有権移転登記
- 売却代金の分配
- 譲渡所得税の計算
- 確定申告の準備
1年~1年3ヶ月
税務申告・完了の期間
確定申告と最終的な手続きを完了させる期間。税務申告期限を守って適切な処理を行います。
12~13ヶ月
- 譲渡所得の計算確定
- 確定申告書の作成
- 特例適用の最終確認
- 必要書類の最終整理
- 税理士との最終確認
13~15ヶ月
- 確定申告書の提出(3月15日まで)
- 税額の納付
- 還付金の受取(該当者)
- 関係書類の保管
- 手続きの完全終了
見落とし厳禁!重要な期限リマインダー
絶対期限(法定期限)
- 相続放棄:3ヶ月以内
- 相続税申告:10ヶ月以内
- 所得税申告:翌年3月15日まで
- 相続登記:3年以内(義務化)
特例制度の期限
- 3,000万円控除:3年以内売却
- 空き家特例:2023年末まで
- 取得費加算:相続税申告期限から3年
- 軽減税率:10年超所有要件
最適なタイミング
- 売却開始:相続から6ヶ月後
- 契約締結:相続から10ヶ月後
- 引渡完了:相続から1年後
- 確定申告:売却翌年2月
💡 早期相談のメリット:期限に余裕を持って進められ、有利な条件での売却が可能になります
段階別の注意点とコツ:成功のポイント
初期段階(0-3ヶ月)のコツ
- 早期の専門家相談で全体計画を立てる
- 相続人全員への早期連絡で合意形成の基盤作り
- 重要書類の集約で後の手続きをスムーズに
- 不動産の現況確認で課題の早期発見
中期段階(3-9ヶ月)のコツ
- 複数社での査定比較で適正価格を把握
- 特例制度の事前確認で節税効果を最大化
- 売却条件の明確化で交渉をスムーズに
- 境界・権利関係の整理でトラブル予防
最終段階(9ヶ月-完了)のコツ
- 契約条件の詳細確認でトラブル防止
- 税務申告の事前準備で期限内完了
- 書類の適切な保管で将来の照会に対応
- 最終確認の徹底で手続き漏れ防止
HomeLinQ「スケジュール管理サポート」
「期限管理が大変」「何から手をつけて良いかわからない」
そんな方のために、HomeLinQでは個別のスケジュール管理サポートを提供しています。
個別タイムライン作成
お客様の状況に合わせた詳細なスケジュール表を作成
期限リマインダー
重要な期限の事前通知で手続き漏れを完全防止
進行管理サポート
各段階での進捗確認と次のステップのご案内
スケジュール管理サポートも無料相談で承ります。
相続発生直後からサポート開始できます。
全体の流れがわかりましたね!
次は、よくあるトラブルと回避方法について確認していきましょう 🚨
事前対策で安心!よくあるトラブルと効果的な回避方法【2025年版】
転ばぬ先の杖!トラブルを未然に防ぐ知恵
相続不動産の売却では、予期しないトラブルが発生することがあります。「こんなはずじゃなかった...」「もっと早く知っていれば...」という後悔をしないために、事前の対策が重要です。
ここでは、実際によく起こるトラブル事例と、その効果的な予防・解決方法をご紹介します。知っているだけで避けられるトラブルがたくさんありますので、ぜひ参考にしてください。
トラブル分類の概要:どんな問題が起こりやすい?
相続人関連トラブル
- 意見の不一致
- 連絡が取れない相続人
- 遺産分割協議の難航
- 感情的な対立
法的・手続きトラブル
- 期限切れ・申告漏れ
- 書類の不備・紛失
- 権利関係の複雑化
- 税務上の問題
不動産関連トラブル
- 境界問題・越境
- 隠れた瑕疵・欠陥
- 価格評価の相違
- 売却条件の問題
専門家関連トラブル
- コミュニケーション不足
- 費用の予想外の発生
- 専門家の選択ミス
- 連携不足の問題
相続人関連トラブル:家族間の問題を円滑に解決
ケース1:売却vs保有で意見が分かれる
よくある状況
- 「思い出の家だから売りたくない」
- 「管理が大変だから早く売却したい」
- 「もう少し価格が上がってから」
- 「賃貸に出して収益を得たい」
効果的な解決方法
- 客観的なデータを共有(査定書、維持費用、税負担等)
- 各選択肢のメリット・デメリットを整理
- 感情論ではなく数字で話し合い
- 専門家を交えた家族会議の開催
ケース2:連絡が取れない・非協力的な相続人
よくある状況
- 疎遠になっている兄弟姉妹
- 海外在住で連絡困難
- 感情的な理由で拒否
- 書類への署名・押印を拒否
効果的な解決方法
- 弁護士・司法書士を通じた正式な連絡
- 内容証明郵便での意思確認
- 調停制度の活用
- 十分な説明と誠意ある対応
ケース3:過去の確執が影響する感情的対立
よくある状況
- 生前の介護負担の差への不満
- 「長男だから」「長女だから」の固定観念
- 過去の金銭的援助への不公平感
- 配偶者同士の対立
効果的な解決方法
- 中立的な第三者(弁護士等)の仲介
- 相続人以外の配偶者は協議から除外
- 過去ではなく現在の状況に焦点
- 冷却期間を設けて段階的に解決
法的・手続きトラブル:期限と書類の管理で防ぐ問題
ケース1:重要な期限の見落とし・申告漏れ
発生しやすい問題
- 相続税申告期限(10ヶ月)の超過
- 特例制度期限(3年)の失効
- 確定申告期限(3月15日)の遅延
- 相続登記義務化(3年)の対応漏れ
予防・対策方法
- 相続発生後の速やかな専門家相談
- 期限管理表の作成・共有
- リマインダー機能の活用
- 余裕を持ったスケジュール設定
ケース2:重要書類の不備・紛失
発生しやすい問題
- 権利証・登記識別情報の紛失
- 購入時契約書の行方不明
- 印鑑証明書の有効期限切れ
- 戸籍謄本の取得漏れ
予防・対策方法
- 早期の書類確認・整理
- 紛失時の代替手続きの確認
- 有効期限の事前チェック
- 司法書士による本人確認情報作成
ケース3:予期しない税務上の問題
発生しやすい問題
- 想定以上の譲渡所得税
- 特例制度の適用要件未充足
- 取得費の証明困難
- 贈与税の課税リスク
予防・対策方法
- 売却前の税務シミュレーション
- 税理士による事前確認
- 特例適用要件の詳細チェック
- 取得費証明書類の事前準備
不動産関連トラブル:物件固有の問題を事前に把握
ケース1:境界線の不明確・越境問題
発生しやすい問題
- 隣地との境界線が不明確
- 建物・塀の越境
- 測量図と現況の相違
- 隣人との認識の相違
解決・対策方法
- 土地家屋調査士による測量・境界確定
- 隣地所有者との事前協議
- 境界確定書の作成
- 越境問題の解決策検討
ケース2:売却後に発覚する隠れた瑕疵・欠陥
発生しやすい問題
- シロアリ被害・腐食
- 雨漏り・水害履歴
- 地盤沈下・土壌汚染
- 近隣の迷惑施設
解決・対策方法
- 事前のインスペクション(建物診断)
- 詳細な物件調査書の作成
- 既知の問題の明確な告知
- 瑕疵担保責任の適切な設定
ケース3:相続人間での価格評価の相違
発生しやすい問題
- 「もっと高く売れるはず」の期待
- 感情的価値と市場価値の乖離
- 複数査定結果の大きな差
- 売却タイミングへの意見相違
解決・対策方法
- 複数社による査定の実施
- 不動産鑑定士による正式鑑定
- 周辺相場データの客観的分析
- 市場動向の専門家による説明
トラブル予防の総合対策:成功の秘訣
コミュニケーション重視
- 定期的な家族会議
- 情報の透明性確保
- 感情論より客観的データ
- 第三者の中立的意見活用
早期の専門家相談
- 相続発生後の速やかな相談
- 複数分野の専門家連携
- 問題発生前の予防的対応
- セカンドオピニオン活用
書面での記録・確認
- 協議内容の議事録作成
- 合意事項の書面化
- 期限管理表の共有
- 重要書類の適切保管
💡 重要:小さな問題も放置せず、早めの対応で大きなトラブルを防ぐことができます
HomeLinQ「トラブル予防・解決サポート」
「問題が起きてから慌てたくない」「事前にリスクを把握したい」
そんな方のために、HomeLinQでは包括的なトラブル予防・解決サポートを提供しています。
リスク事前診断
売却前の包括的リスク診断で潜在的な問題を早期発見
家族会議ファシリテート
中立的な立場での家族会議進行で建設的な話し合いをサポート
緊急トラブル対応
24時間体制の緊急相談で突発的な問題にも迅速対応
トラブル予防診断も無料相談で承ります。
問題発生前の予防的対応が最も効果的です。
トラブル回避方法がわかりましたね!
次は、専門家との効果的な連携方法について確認していきましょう 🤝
成功の鍵は連携!専門家チームの最適化戦略【2025年版】
チーム戦で臨む!専門家との効果的な連携方法
相続不動産の売却は複数の専門分野にまたがる複雑な手続きです。「誰に何を相談すれば良いの?」「専門家同士がうまく連携してくれるの?」という不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、適切な専門家の選び方から効果的な連携方法まで、成功する専門家チーム構築のコツをお伝えします。一人で悩まず、信頼できるプロチームと一緒に進めていきましょう。
専門家チーム構成:それぞれの役割と重要性
司法書士
【登記・法的手続きの専門家】
- 相続登記の申請
- 遺産分割協議書作成
- 所有権移転登記
- 各種書類の準備・確認
税理士
【税務・申告の専門家】
- 相続税申告
- 譲渡所得税の計算
- 特例制度の適用
- 確定申告の代行
不動産会社
【売却・査定の専門家】
- 不動産査定・価格設定
- 売却活動・買主探し
- 契約・決済のサポート
- 市場動向の情報提供
弁護士
【法的トラブル・紛争解決の専門家】
- 遺産分割協議の調整
- 相続トラブルの解決
- 調停・審判の代理
- 法的リスクの回避
土地家屋調査士
【測量・境界確定の専門家】
- 土地の測量・境界確定
- 越境問題の解決
- 登記情報の調査
- 現況測量図の作成
不動産鑑定士
【適正価格評価の専門家】
- 不動産の正式鑑定
- 相続税評価の確認
- 適正価格の算定
- 争いがある場合の中立評価
失敗しない専門家選びのポイント
ポイント1:相続不動産に特化した専門性と豊富な実績
確認すべき専門性
- 相続案件の取扱実績(年間何件程度か)
- 類似ケースの経験(複雑な相続、共有名義等)
- 最新の法改正への対応(2024年相続登記義務化等)
- 他の専門家との連携経験
注意すべきポイント
- 一般的な業務のみの経験
- 相続税制への理解不足
- 他分野専門家との連携不慣れ
- 最新情報のキャッチアップ不足
ポイント2:わかりやすい説明力と親身なコミュニケーション
良い専門家の特徴
- 専門用語を分かりやすく説明
- 複数の選択肢とメリット・デメリットを提示
- 質問に対して丁寧に回答
- 進捗状況を定期的に報告
避けるべき専門家
- 説明が専門用語ばかりで理解困難
- 一方的に自分の意見を押し付ける
- 連絡が取りにくい・返答が遅い
- 費用の説明が不透明
ポイント3:明確で納得できる料金体系
確認すべき事項
- 基本料金と追加料金の内訳
- 成功報酬の有無と条件
- 実費(登記費用等)の扱い
- 見積書の詳細な項目
費用関連の注意点
- 極端に安い料金には理由がある
- 追加料金の発生条件を事前確認
- 複数の専門家から見積を取得
- 料金だけでなく総合的に判断
スムーズな進行を実現!効果的な専門家連携方法
パターン1:中心型連携(推奨)
仕組みと特徴
- コーディネーター役を一人決める(司法書士や不動産会社等)
- 全体進行管理と情報共有を担当
- 他の専門家との橋渡し役
- お客様は主に一人の窓口とやり取り
メリット
- 情報伝達がスムーズ
- 重複や漏れを防止
- お客様の負担軽減
- 専門家間の連携強化
パターン2:分散型連携
仕組みと特徴
- お客様が各専門家と直接やり取り
- 必要に応じて専門家同士が連絡
- 案件ごとに最適な専門家を選択
- 柔軟な体制構築が可能
注意点
- お客様の調整負担が大きい
- 情報共有の漏れリスク
- スケジュール管理の複雑化
- 専門家間の認識ズレ
連携成功のコツ
定期的な進捗共有
週次または月次の進捗報告会を設定し、全体の状況を把握。遅れや問題を早期発見。
情報共有ツールの活用
共有フォルダやチャットツールで情報を一元管理。重要書類の共有や連絡履歴の記録。
役割分担の明確化
誰が何をいつまでに行うかを明確に設定。重複作業や責任の曖昧さを防止。
段階別専門家活用戦略:最適なタイミングで最適な専門家を
初期段階(相続発生~3ヶ月)
優先度高:司法書士
相続人調査、遺産分割協議書作成、基本的な手続きの整理
必要に応じて:弁護士
相続人間でトラブルの兆候がある場合、早期相談
中期段階(3ヶ月~9ヶ月)
優先度高:不動産会社・税理士
査定・売却活動開始、税務シミュレーション実施
必要に応じて:土地家屋調査士
境界問題や測量が必要な場合の早期対応
最終段階(9ヶ月~完了)
優先度高:司法書士・税理士
所有権移転登記、確定申告書作成・提出
サポート:不動産会社
決済・引渡し手続き、アフターフォロー
💡 重要:全ての段階で情報共有を密にし、チーム一丸となって進めることが成功の鍵です
HomeLinQ「専門家ネットワーク」
「信頼できる専門家をどう見つければ良いの?」「連携してもらえるか心配」
そんな方のために、HomeLinQでは厳選された専門家ネットワークをご用意しています。
厳選された専門家
相続不動産に特化し、豊富な実績を持つ専門家のみを厳選
最適なチーム編成
お客様の状況に応じて最適な専門家チームを編成・コーディネート
ワンストップサポート
HomeLinQが窓口となり、専門家との調整・進行管理を一元化
専門家のご紹介・チーム編成も無料相談で承ります。
まずはお客様の状況をお聞かせください。
専門家連携の重要性がわかりましたね!
最後に、HomeLinQの総合サポートについて確認していきましょう 🏠
HomeLinQと一緒に、安心の相続不動産売却を実現しませんか?【2025年版】
お疲れ様でした!ここまでの道のりを振り返ってみましょう
相続不動産の売却について、この記事では多くのことをお伝えしました。「こんなに複雑なんだ...」「一人で全部やるのは大変そう...」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
でも安心してください。適切なサポートがあれば、決して怖いものではありません。HomeLinQでは、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なサポートをご提供しています。一緒に乗り越えていきましょう!
この記事で学んだ重要なポイント【完全チェックリスト】
法的手続き・期限管理
- 相続登記義務化(3年以内)の対応
- 遺産分割協議書作成・換価分割活用
- 相続人間の合意形成戦略
- 期限管理とスケジュール設定
費用・税務・節税対策
- 売却費用の詳細分析(2025年版)
- 節税特例制度の最大活用
- 税務申告の流れとタイミング
- 確定申告の準備・手続き
書類準備・手続き管理
- 必要書類の完全チェックリスト
- 効率的な書類取得順序
- 段階別手続き管理
- 書類不備の予防策
トラブル予防・専門家連携
- よくあるトラブルと回避方法
- 専門家選びのポイント
- 効果的な連携システム構築
- 段階別専門家活用戦略
✨ これらの知識があれば、相続不動産売却の85%は成功に導けます!
なぜHomeLinQが選ばれるのか?【6つの安心サポート】
【1】ワンストップサービス
査定から売却完了まで、すべての手続きを一括サポート。複数の窓口をたらい回しされる心配はありません。
【2】厳選専門家ネットワーク
相続不動産に特化した専門家のみを厳選。司法書士・税理士・弁護士などと密に連携します。
【3】透明で安心の料金体系
初回相談は完全無料。料金も事前に明確にご提示。隠れた費用や追加料金の心配はありません。
【4】安心の24時間サポート
急な疑問や不安にも即座に対応。専門スタッフがいつでもお客様をサポートします。
【5】豊富な実績と高い信頼
相続不動産売却実績2,000件以上。お客様満足度95%の実績で安心してお任せいただけます。
【6】万全のアフターケア
売却完了後も安心。税務申告サポートから今後の資産運用相談まで継続的にサポート。
お客様からの喜びの声【実際の成功事例】
相続人5名の複雑なケース
東京都・Aさま(50代)
「5人の相続人がいて、最初は意見がバラバラでした。でもHomeLinQさんが間に入って調整してくださり、6ヶ月で無事売却完了。税務面でも300万円の節税ができました!」
遠方物件の売却
大阪府・Bさま(40代)
「東京在住で、故郷の実家を相続。現地に行けない私のために、すべて代行していただきました。安心してお任せできて本当に助かりました!」
税務トラブル未然防止
埼玉県・Cさま(60代)
「税務申告に不安がありましたが、専門の税理士さんを紹介いただき、特例制度も最大限活用できました。知らなかったら大損するところでした!」
💝 多くのお客様から「HomeLinQに頼んで良かった」とのお声をいただいています
さあ、次のステップへ!今すぐできる3つのアクション
まずは無料相談から
お客様の状況をお聞かせください。相続の状況、物件の詳細、ご不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。
✓ 相談料:完全無料
✓ 所要時間:30分程度
✓ オンライン相談も可能
正確な査定で価値を把握
相続不動産の適正価値を正確に査定します。税務申告用の査定書も作成可能です。
✓ 査定料:完全無料
✓ 査定書作成も無料
✓ 税務申告にも使用可能
オーダーメイドプラン作成
お客様だけの最適な売却プランを作成。スケジュール、費用、手続きまで詳細にご提案します。
✓ プラン作成:無料
✓ 詳細スケジュール付き
✓ 修正・調整も可能
今すぐ無料相談・査定のお申し込みを!
相続不動産の売却は、早めの行動が成功の鍵です
まずはお気軽にご相談ください。専門スタッフがお客様をお待ちしています。
安心の完全無料相談 | 秘密厳守 | しつこい営業は一切ありません
一人で悩まず、一緒に解決していきましょう
相続不動産の売却は人生の大きな決断です。「失敗したらどうしよう」「損をしたらどうしよう」という不安をお持ちの方も多いでしょう。
でも安心してください。HomeLinQには、同じような状況を乗り越えた多くのお客様の成功事例があります。あなたも必ず成功できます。
HomeLinQが、あなたの相続不動産売却を全力でサポートします!
さらに詳しく学びたい方におすすめの関連記事
離婚時の不動産分与
離婚時の不動産売却について詳しく解説
空き家管理サービス
東京都の空き家管理について詳しく解説
債務整理と不動産
債務整理時の不動産売却について詳しく解説
この記事がお役に立ちましたら、ぜひ無料相談でお話をお聞かせください。
最終更新日:2025年5月14日 | 監修:HomeLinQ編集部